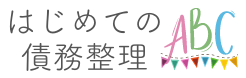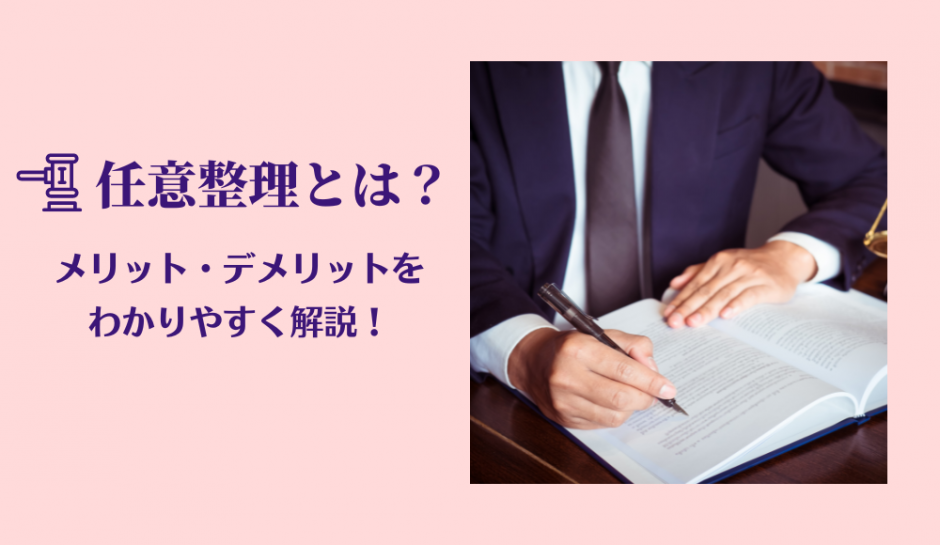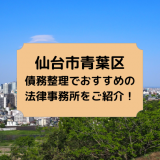任意整理は債権者と交渉し、利息の減免や返済期間の延長などを行い返済プランを見直します。個人再生や自己破産と違い裁判所を介さずに手続きできます。
他の債務整理手続きと比較して手続きが簡単で、資産を守れる、費用が安いなどの面で優れており、最もおすすめの債務整理と言えます。
また家族や職場に知られにくいというメリットもあり。ただし、信用情報への登録や元金自体の減額は原則ないことなどデメリットも十分に理解しておくことが大切です。
この記事では任意整理とはどのような手続きで、どんなメリット・デメリットがあるのか詳しくお伝えしていきます。
目次
任意整理の基本情報
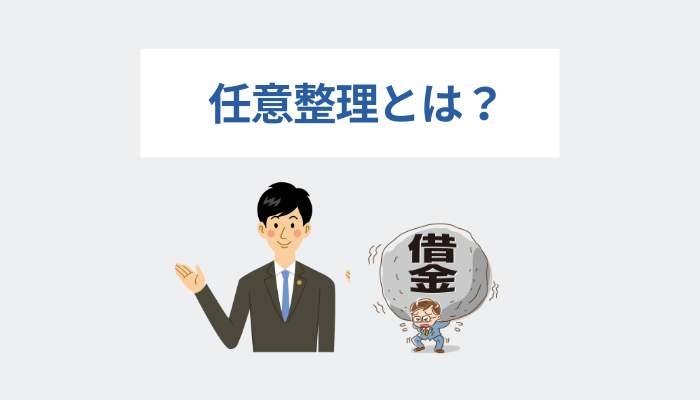
任意整理とは
任意整理は、借金の返済が困難になった場合に、裁判所を介さずに債権者(消費者金融やクレジットカード会社など)と直接交渉し、返済条件(主に利息や返済期間)を見直してもらう債務整理の一種です。
法的な借金減額の手段であり、当然ながら人生終わりなどではありません。借金問題を解決するための現実的な選択肢の一つです。
弁護士や司法書士が代理人となって手続きを進めるケースが多いのですが、本人が自力で交渉することも可能です。
ただし、専門的な知識や交渉力が求められるため、専門家に依頼するのが一般的です。
任意整理の特徴
裁判所を介さず、債権者と直接または代理人を通じて交渉し、和解によって返済計画を立て直します。
主に将来利息や遅延損害金をカットし、元金のみを3~5年(36~60回)で分割返済する内容が一般的です。
利息制限法を超える「グレーゾーン金利」で返済していた場合、引き直し計算によって元本自体が減額されることもあります。
整理する債権者を選ぶことができ、保証人付きの借金や自動車ローンなどを対象から外すことも可能です。
任意整理は、他の債務整理(自己破産・個人再生等)と比べて手続きが簡単で、外部に知られにくいというメリットがあります。
任意整理は、基本的に借金に苦しむすべての人におすすめできますが、事業を続けたい個人事業主や将来的に借金完済を目指す人など、任意整理をしない方がいい場合も一部あります。
任意整理は債務整理の一つの方法
「債務整理する」という表現は、この記事で解説する任意整理のほか、自己破産・個人再生など、その人の手続きにあわせて借金問題の解決を目指すことを意味します。
関連記事:債務整理と任意整理の違いとは?
任意整理の主な条件
安定した収入があること
任意整理後は元本のみを3~5年(36~60回)で分割返済するのが一般的です。
月々の返済額を無理なく支払える安定した収入(給与、年金、事業収入など)が必要です。正社員だけでなく、アルバイトやパート、年金生活者、個人事業主でも安定収入があれば利用できます。
生活費や他の支出を差し引いても、返済が現実的な範囲(月々の返済額が手取り収入の2~3割程度に収まる)であることが望ましいです。
3~5年で完済できる見込みがあること
任意整理後の借金を原則3~5年で完済できることが条件です。
例えば、借金総額が300万円であれば、5年(60回)で返済する場合は月々5万円の返済が必要です。生活費を差し引いた手取り収入から、この金額を無理なく支払えるかが判断基準となります。
返済計画が現実的であること
生活費や他の支出を差し引いても、月々の返済額が手取り収入の2~3割程度に収まることが望ましいとされています。
返済継続の意思があること
任意整理は自己破産と異なり、返済義務がなくなるわけではありません。和解後も返済を続ける強い意思が必要です。
債権者が交渉に応じること
任意整理は債権者との合意が前提です。債権者が交渉に応じなければ任意整理は成立しません。これまでに返済をしてきた実績があると、債権者は交渉に応じやすくなります。
任意整理できないケース
- 収入が全くない、または収入が不安定で返済の見込みが立たない場合
- 借金総額が大きすぎて、3~5年で完済できる見込みがない場合
- 債権者が交渉に応じない場合(例:個人間の借金、一部の業者)
担保権や所有権留保がついているローン(自動車ローンや住宅ローン等)は、任意整理の対象にすると財産を失うリスクがあるため、通常は対象外とします。
また、保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、保証人に一括請求がいくため、保証人に迷惑をかけたくない場合は対象から外します。
任意整理と他の債務整理の違い
| 主な特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を介さず債権者と直接交渉し返済条件を見直す | ・手続きが簡単 ・外部に知られにくい ・対象債権者を選べる |
・借金がゼロになるわけではない ・債権者の同意が必要 |
| 自己破産 | 裁判所を通じて借金の返済義務を免除 | 借金が全額免除される | ・財産処分 ・職業制限などのデメリットあり |
| 個人再生 | 裁判所を通じて借金を大幅減額し原則3年で分割返済 | ・住宅ローン特則で自宅を守れる ・借金が大幅減額 |
・手続きが複雑 ・一定の収入が必要 |
| 過払い金請求 | 払いすぎた利息を返還請求 | ・払いすぎた分が戻る ・債務がなくなる場合もある |
対象はグレーゾーン金利での借入のみ |
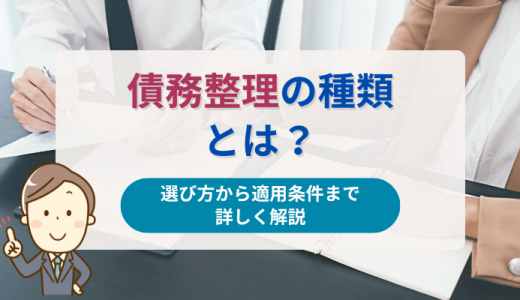 債務整理の種類とは?選び方から適用条件まで詳しく解説
債務整理の種類とは?選び方から適用条件まで詳しく解説
自己破産
裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きで、任意整理よりも強力ですが、職業制限や財産処分などのデメリットがあります。
関連記事:任意整理と自己破産の違いとは / 自己破産の依頼におすすめの法律事務所
個人再生
裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済する手続きで、住宅ローン特則を利用すれば自宅を守ることも可能です。任意整理よりも借金減額効果が大きいですが、手続きが複雑です。
関連記事:任意整理と個人再生の違いとは / 個人再生におすすめの法律事務所
過払い金請求
過去にグレーゾーン金利で返済していた場合に、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。任意整理の過程で過払い金が判明し、債務がなくなる場合もあります。
関連記事:過払い金請求とは / 過払い金診断は怪しい?
任意整理のデメリット
任意整理には次のようなデメリットがあります。
- ブラックリストに登録される
- 減額されるのが債務整理の中では一番少ない
- 債権者の協力が得られないケースがある
- 収入がない・少ないような場合には利用できない
ブラックリストに登録される
任意整理を行うと、信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」状態となります。
事故情報の登録期間は、完済から5年が一般的です。任意整理の返済期間が3~5年かかるため、手続き開始からブラックリスト状態が8年程度続くこともあります。
この期間中は、新規のローンやクレジットカードの作成・更新、携帯電話の分割購入などが難しくなります。
事故情報は永続するものではなく、完済から5年経過すれば消去されます。
なお、延滞が3か月以上続いた場合も同様に事故情報が登録されるため、任意整理を避けても遅延があれば同じ結果となることがあります。
 任意整理によるブラックリストについて徹底解説!いつからいつまで登録される?
任意整理によるブラックリストについて徹底解説!いつからいつまで登録される?
減額される幅が他の債務整理より小さい
任意整理は、主に将来利息や遅延損害金のカットを目的とし、元金自体の減額は基本的にありません。
例外として、過払い金(利息制限法を超える金利で借りていた場合)が発生している場合は、元金が減ることもあります。
自己破産は借金が全額免除され、個人再生は借金が大幅に減額されるのに対し、任意整理は返済負担が最も残る手続きです。
債権者の協力が得られないケースがある
任意整理は債権者との合意が前提であり、債権者が交渉に応じない場合や、返済条件が厳しい場合は和解が成立しないことがあります。
特に、取引期間が短い、返済実績がない、債権者の経営状態が悪い、担保がある場合などは交渉が難航することがあります。
ただし、任意整理に全く応じない業者は少数で、多くの業者は交渉に応じてくれます。一部の債権者が応じない場合でも、他の債権者との任意整理は可能です。
債務整理の経験が豊富な専門家に依頼することで、有利に交渉を進められます
収入がない・少ない場合には利用できない
任意整理は元金を分割返済する手続きのため、安定した収入がない場合や、分割返済額を支払えるだけの収入がない場合には利用できません。
ただし、無職でも就職予定があり将来的に収入が見込める場合や、家族の協力で返済が可能な場合は任意整理ができることもあります。
返済期間は原則3~5年(36~60回)が上限ですが、債権者との交渉次第でさらに長期の分割が認められるケースもあります。
クレジットカードが利用停止となる
任意整理を行うと、既存のクレジットカードは原則として利用停止・解約となります。
そのため、ネットショッピングやサブスクリプションサービス、公共料金の自動引き落としなど、クレジットカード決済が前提となっている支払い方法が利用できなくなります。
また、ETCカードや家族カードなど、クレジットカードに付随するサービスも同時に使えなくなります。
クレジットカードに貯まっていたポイントやマイル、キャッシュバック特典なども、カード解約と同時に失効するため注意して下さい。
なお、任意整理後は信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるため、最低5年間は新たなクレジットカードの審査に通らなくなります。
ネット決済などにはデビットカードが代替手段として利用できます
 債務整理(任意整理)してもクレジットカードは使える?新規発行はできるのか
債務整理(任意整理)してもクレジットカードは使える?新規発行はできるのか
任意整理のメリット
一方で任意整理には、多くのメリットがあります。
- 原則として利息がカット
- 3年~5年の長期の分割払い
- 官報に掲載されない
- 職業制限・住居移転制限などがない
- 複雑な申し立て書類の作成が不要
- 裁判所等に呼び出されない
- 弁護士・司法書士に依頼すれば取り立てを受けなくなる
- 訴訟されるのを止められる可能性がある
- 連帯保証人がいる債務・担保がある債務などを外すことが可能
- 他の手続きに比べて比較的バレずらい
原則として将来利息・遅延損害金がカットされる
任意整理では、将来発生する利息や遅延損害金をカットすることが交渉の中心となります。
返済した分がすべて元金の返済に充てられるため、返済総額が減り、完済までの期間も短くなります。
ただし、交渉の結果や債権者の方針によっては、利息が一部残る、またはカットされない場合もあります。
「原則として」としたのは、借入期間が短い・すでに訴訟がされているなどで、貸金業者が利息の主張をする可能性は0とはいえない場合があるためです。
3年~5年の分割返済が可能
任意整理では、元金のみを3年~5年(36~60回)の分割払いにしてもらえるのが一般的です。
返済額や期間は債権者との交渉によって決まりますが、無理のない返済計画を立てやすくなります。
例えば、元金が30万円である場合、毎月5,000円の60回分割としてもらえる可能性があります。
長期の分割返済にできる
官報に掲載されない
自己破産や個人再生と異なり、任意整理は裁判所を通さず債権者との直接交渉で行うため、官報に掲載されることはありません。
そのため、周囲に債務整理をしたことが知られるリスクが低くなります。
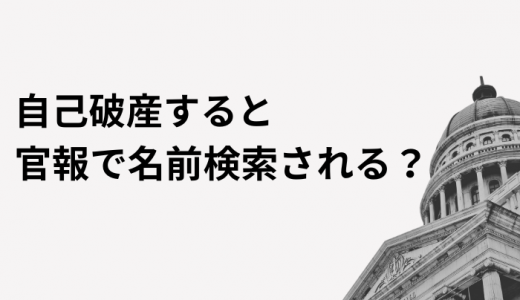 自己破産で個人情報が官報に掲載される!名前検索はされるの?
自己破産で個人情報が官報に掲載される!名前検索はされるの?
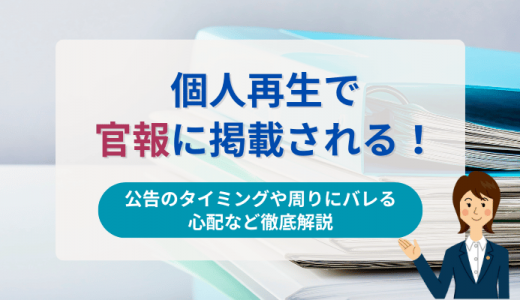 個人再生で官報に掲載される!公告のタイミングや周りにバレる心配など徹底解説
個人再生で官報に掲載される!公告のタイミングや周りにバレる心配など徹底解説
職業制限・住居移転制限がない
自己破産のような一部の職業制限や住居移転制限が任意整理にはありません。現在の仕事や生活に直接的な制限がかかることはありません。
複雑な申し立て書類の作成が不要
任意整理は裁判所を通さないため、自己破産や個人再生のような複雑な申立書類や添付書類の作成が不要です。
手続きが比較的簡単で、専門家に依頼すればほぼすべて代行してもらえます。
裁判所への出頭が不要
任意整理では裁判所への出頭や面談が不要なため、平日昼間に仕事を休む必要がありません。
日常生活への影響が少ないのも大きなメリットです。なお、自己破産・個人再生を選ぶと裁判所への出頭や面談が必要となります。
弁護士・司法書士に依頼すれば督促・取り立てが止まる
弁護士や司法書士に依頼し受任通知が債権者に届くと、貸金業法により督促や取り立てが停止します。
そのため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
貸金業者は貸金業法に従って、正当な理由がない限り本人に督促することができなくなります。
訴訟を止められる可能性がある
任意整理の交渉を開始すれば、債権者が訴訟を起こすのを控えることが多く、すでに訴訟中の場合でも和解によって訴訟を取り下げてもらえる場合があります。
ただし、必ず訴訟が止まるとは限らず、債権者の判断によります。
連帯保証人付きや担保付きの債務を対象外にできる
任意整理は対象とする債権者を選べるため、連帯保証人がいる借金や担保付きローン(自動車ローンや住宅ローンなど)を手続きから外すことができます。
これにより、保証人や担保物件への影響を避けることができます。
たとえば、連帯保証人である親に迷惑をかけたくない場合には、奨学金については任意整理から外して従来通り返済をすることも可能です。
他の手続きよりバレにくい
任意整理は裁判所を介さず、郵送物や書類のやり取りも最小限で済むため、家族や職場に知られにくい傾向があります。
自己破産や個人再生は、様々な書類を裁判所に提出したり、管財手続になる場合には郵送物が管財人に送られるなど(自己破産のケース)、家族にバレる可能性が任意整理よりも高い
任意整理の流れ
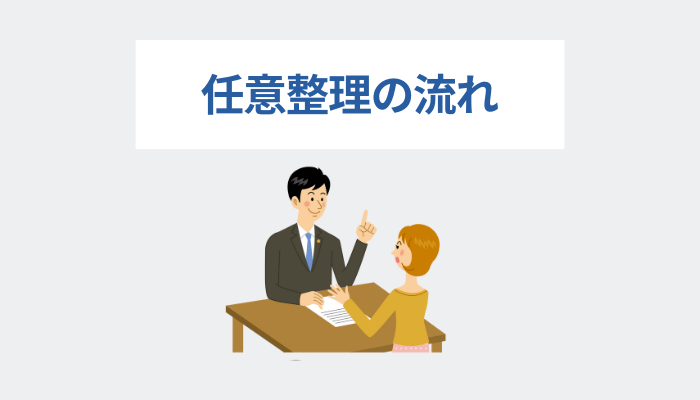
任意整理の流れについて確認しましょう。裁判所を通さずに進めるため、比較的短期間で借金問題の解決を目指すことができます。
- 弁護士・司法書士に相談する
- 受任通知を送付する
- 取引履歴を取り寄せる
- 引き直し計算を行う
- 弁護士・司法書士と交渉前に打ち合わせを行う
- 弁護士・司法書士が貸金業者と交渉をする
- 任意整理が成立し返済開始
相談から返済開始までの期間は、通常3~6か月程度かかります
STEP1:専門家への相談・依頼
まずは弁護士や司法書士に相談します。多くの事務所で初回相談は無料です。
電話やメール、事務所のウェブサイトから予約できます。最近はSNSやチャットでの相談窓口を設けている事務所もあります。
借入先や借入額、収入・支出状況などを整理しておくとスムーズです。費用については分割払いに対応している事務所が多いです。
任意整理は自力でも可能ですが、債権者との交渉や書類の準備が難航する場合が多いため、専門家に依頼するのが一般的です。
STEP2:委任契約の締結・受任通知の送付
相談の結果、正式に依頼する場合は委任契約を結びます。契約内容や費用は事前にしっかり確認しましょう。
依頼後、弁護士・司法書士が債権者に「受任通知」を送付します。これにより債権者からの督促や取り立てが法律上ストップします。
STEP3:取引履歴の開示請求・債務額の調査
債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な債務額を調査します。取引履歴の開示には1~2か月程度かかる場合があります。
STEP4:引き直し計算・過払い金の確認
取引履歴をもとに利息制限法に基づく引き直し計算を行い、実際の債務額を算出します。
過払い金が発生していれば返還請求も行います。
依頼者に返還すべき義務のある、グレーゾーン金利での支払いがあったかどうかを調べる
STEP5:返済計画(和解案)の作成・依頼者との打ち合わせ
引き直し計算後、依頼者の収入や生活状況を踏まえ、無理のない返済計画(任意整理案)を作成します。
返済可能額や期間(通常3~5年)を検討し、依頼者と打ち合わせを行います。なお、プール金(返済準備金)を積み立てることを推奨する事務所もあります。
STEP6:債権者との交渉・和解契約の締結
弁護士・司法書士が債権者と交渉し、主に将来利息のカットや分割返済(3~5年程度が一般的)について合意を目指します。
交渉がまとまれば和解契約書を取り交わします。
STEP7:返済開始
和解契約に基づき、指定された方法で返済を開始します。返済方法は、債権者の指定口座への振込が一般的ですが、弁護士・司法書士による弁済代行を利用できる場合もあります。
完済すれば任意整理は終了です。経済状況が改善した場合は一括返済も可能です。
任意整理の費用の相場
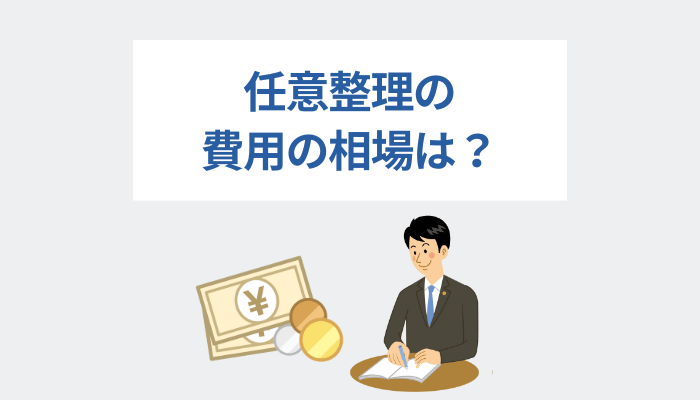
「任意整理の費用」には、次のような項目があります。
| 費用項目 | 相場 (1社あたり) |
備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 0円 (無料相談が主流) |
初回無料の事務所が多い |
| 着手金 | 2万円~5万円 | 分割払い対応の事務所も多い |
| 報酬金 (解決報酬金) |
0円~2万円 (上限2万円・税抜) |
和解成立時に発生、設定しない事務所もある |
| 減額報酬 | 減額分の10%~11% | 減額がない場合は発生しない、上限11% |
| 過払い金報酬 | 回収額の20%~25% | 過払い金が発生した場合のみ |
| 実費 | 数千円~2万円程度 | 郵送・通信費・印紙代など |
相談料
任意整理の相談料は、以前は30分5,000円程度が一般的でしたが、現在は多くの弁護士・司法書士事務所で「初回相談無料」や「借金相談無料」としているところが多くなっています。
法テラスや市区町村、弁護士会・司法書士会などの公的機関でも無料相談が利用できます。
着手金
着手金は、依頼時に発生する費用で、案件の成否にかかわらず支払う必要があります。相場は1社あたり2万円〜5万円程度です。
債権者が複数の場合は、その分だけ費用が加算されます。分割払いに対応している事務所も多く、まとまった金額を一度に用意できない場合でも相談可能です。
着手金無料をうたう事務所では、報酬金や減額報酬が高額に設定されている場合もあるので、全体の費用を確認することが重要です。
報酬金(解決報酬金・基本報酬金)
報酬金は、任意整理が成立し和解契約が締結された際に発生します。日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会の指針により、1社あたり2万円(税抜)が上限とされています。
事務所によっては報酬金を設定していない場合もあります。
減額報酬
減額報酬は、任意整理によって借金が減額された場合、その減額分の10%~11%(税込)が成功報酬として発生します。上限は11%(税込)です。
近年は、利息制限法による再計算だけでは減額報酬を請求しない事務所も増えています。
過払い金報酬
過払い金が発生し、回収できた場合にのみ発生します。
回収額の20%~25%が相場です(交渉の場合20%、訴訟の場合25%)。
実費
実費は、郵送代や通信費、書類作成費、印紙代などが該当します。数千円~2万円程度が一般的です。
請求方法は事務所によって異なります。実費分のみを請求する、請求しない、または概算で請求する場合などがあります。
訴訟対応や遠方への出張が必要な場合は、追加で交通費や日当がかかることもあります
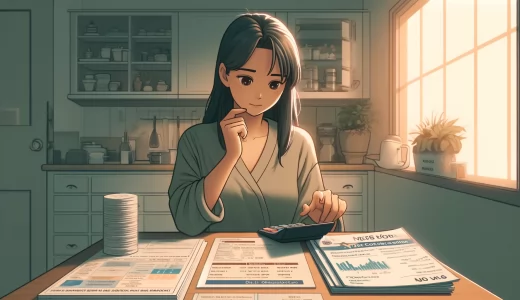 債務整理の費用が払えないときの対処法を徹底解説
債務整理の費用が払えないときの対処法を徹底解説
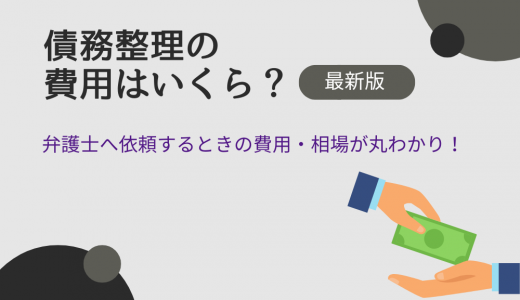 債務整理の費用はいくら?弁護士依頼の相場や費用を払えないときの対処法も解説
債務整理の費用はいくら?弁護士依頼の相場や費用を払えないときの対処法も解説
任意整理に関するよくあるQ&A
任意整理についてよくある質問を確認してみましょう。
住宅ローン・自動車ローンを組むことができるか
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されている間は、住宅ローンや自動車ローンなどの新規ローン審査は非常に厳しく、ほとんどの場合で通過できません。
審査時には信用情報が必ず参照され、事故情報があると「返済能力に問題あり」と判断されるためです。
自動車の購入については、現金一括払いであればローン審査は不要なため、信用情報に事故情報が登録されていても問題なく購入できます。
また、一部の中古車販売店が提供する「自社ローン」は、信用情報を参照しない独自審査のため、任意整理中でも利用できる場合があります。
家族名義でローンを組む、または家族に保証人になってもらう方法もありますが、家族の信用情報や収入などが審査対象となります。
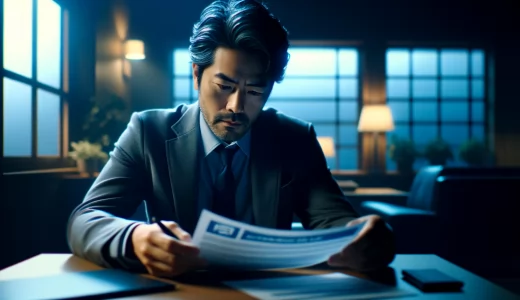 任意整理中でもカーローンに通った例とは?どうしても車が必要な人の対処法
任意整理中でもカーローンに通った例とは?どうしても車が必要な人の対処法
登録期間終了後のローン審査について
事故情報が削除された後(完済から5年程度経過後)は、再び住宅ローンや自動車ローンの審査に通る可能性が出てきます。
ただし、審査は信用情報だけでなく、収入や勤続年数、他の借入状況、健康状態なども総合的に判断されるため、必ずしも通過できるとは限りません。
また、任意整理の対象とした金融機関では、事故情報が消えた後でも内部情報として履歴を保有している場合があり、審査が厳しくなることがあります。
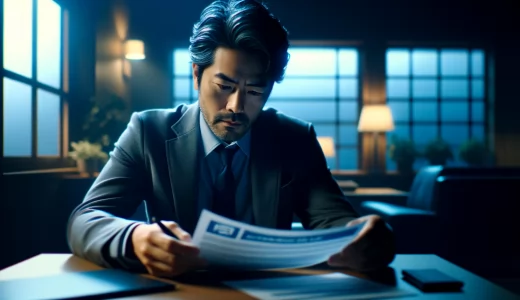 任意整理中でもカーローンに通った例とは?どうしても車が必要な人の対処法
任意整理中でもカーローンに通った例とは?どうしても車が必要な人の対処法
携帯電話の契約・購入をすることができるか
分割購入(割賦契約)について
任意整理後は、携帯電話やスマートフォンの端末を分割払い(割賦契約)で購入することは原則としてできなくなります。
分割購入もローンの一種であり、信用情報機関に事故情報が登録されるため、審査に通らないのが一般的です。
ただし、例外として10万円以下の端末(「少額店頭販売品」)の場合は割賦販売法の例外措置により審査が簡素化されるため、携帯料金や端末代金の滞納がなければ分割契約できる可能性があります。
しかし、これはあくまで例外であり、ほとんどの場合は分割購入は難しいと考えておくべきです。
一括購入・回線契約について
端末を一括で購入する場合や、回線契約そのものは信用情報の審査対象ではないため、任意整理後でも可能です。
また、現在利用中の携帯電話会社を任意整理の対象から外しておけば、分割払い中の端末も引き続き利用できる場合があります。
ただし、通信料や端末代金の滞納がある場合は、強制解約となる可能性が高いです。
家族に内緒で進められるか
任意整理は、家族に知られずに手続きすることが可能です。
債権者からの連絡や郵送物は弁護士・司法書士事務所宛に送付されるため、家族に直接通知が届くことは基本的にありません。
自己破産や個人再生のように家族の協力や書類提出が求められることもありません。
ただし注意点として、家族が連帯保証人になっている債務を任意整理の対象にした場合は、保証人に請求が行くため家族に知られる可能性があります。また、家族カードを利用している場合は、カード利用停止によって発覚することもあります。
任意整理を検討すべきタイミングはいつか
任意整理を検討すべきタイミングは、以下のような状況です。
- 毎月の返済が苦しいと感じるとき
- 返済のために新たな借入を繰り返しているとき
- 延滞・滞納が続いているとき
- 利息の負担が大きく、元本がなかなか減らないとき
- 借金総額が年収の3分の1を超えたとき
借金問題は早めの対応が解決への近道です。返済が困難になった時点で、早めに専門家に相談することが望ましいです。
返済が苦しい、延滞が続くなどの状況になったら、早めに任意整理を検討しましょう。
まとめ
任意整理は、弁護士や司法書士が代理人となり、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と直接交渉して、借金の返済条件(主に利息や返済期間)を見直す債務整理手続きの一つです。
裁判所を介さず、債権者との和解によって返済計画を立て直すため、柔軟な対応が可能です。
任意整理には利息・遅延損害金がつかなくなるという大きなメリットがあります。また、連帯保証人がいる債務などは対象から外すことも可能です。
一方で、減額幅が他の債務整理より少ないなどのデメリットもあります。
任意整理をしたいのであれば、利用条件など詳しくチェックする必要があります。借金問題でお悩みの方は、なるべく早く弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。